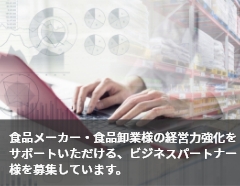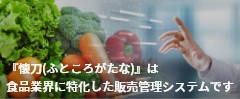猛暑が変える日本の農業 気候危機と向き合う食の現場

はじめに
今年もまた、「過去最も暑い夏」がやってきました。気温が40℃を超える日が各地で記録され、「外に出るのが危険」とさえ言われるような季節が、年々当たり前のようになってきています。この“異常な暑さ”は、私たちの暮らしだけでなく、もっと静かに、しかし確実に、日本の農業を蝕んでいます。気温の上昇は農作物にとって大きな打撃となり、私たちの食卓にも影響を与えています。いま日本にどのような変化が起こり、それに対して農家はどんな対策をしているのか詳しくご紹介します。
日本の気温傾向
数年前から感じている驚異的な暑さ。日本の年間平均気温は年々市場最高を記録し、2024年の年間平均気温は1991年から2020年の30年平均より約1.48℃高く、観測開始の1898年以降で最高記録を更新しました。
世界においても、WMO(世界気象機関)が史上最高の年と認定。産業革命前より平均気温が1.55℃上昇したと報告されています。気温上昇の要因は、エルニーニョ現象と全地球的な温暖化傾向、北太平洋の地表水温が高い状態が重なり、熱波が強化されたと分析されています。地球規模の気候変動が「特別な現象」ではなくなり、私たちの日常に直結する課題となっているのです。
気候変動が農作物に与える影響
我々の食生活に欠かせない農作物は、気温・日照・水分など自然環境に強く依存しています。そのため、気候が変化すると、作物の生育に大きな影響が出ます。特に猛暑は、さまざまな問題を引き起こしています。たとえば、夏野菜の代表トマト。強い日差しで甘くなる反面、極端な高温が続くと、花が咲いても実がつかない「着果障害」が起こりやすくなります。ナスやピーマンも、果実が奇形になったり、皮が硬くなったりと品質が低下します。果物も例外ではありません。ぶどうやモモは、高温で果実が日焼けし、見た目が悪くなるばかりか、味にも影響が出ます。糖度が上がりにくくなったり、酸味とのバランスが崩れたりするのです。
2024年の全体としての全国収穫量の統計値はまだ出ていないものの、日本最大の産直通販サイト「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデンが全国の生産者に対して行った調査では、気候変動の影響で「収穫量が減少した」と答えた生産者は58%、「規格外品が増えている」との回答は29.6%であり、生産者の約70%が例年以下の収穫量と実感しているとの報告もあります。
日本の主食であるお米も、猛暑の影響を受けています。実際、2023年〜2024年の夏は記録的な高温が続き、全国各地で「高温障害米」が増加しました。高温が続くと、米の登熟(お米が実る最終段階)がうまくいかず、「白未熟粒」と呼ばれる白く濁った粒が増加します。見た目が悪く、市場での評価が下がるほか、炊きあがりの味や食感も落ちてしまいます。
農林水産省によると、ここ数年は収穫量も減少傾向にあり、2023年には約716万トンと過去最少クラス。気候の変化が、作物の「量」と「質」の両面に影を落としていることがうかがえます。さらに、気温が上がると困るのは作物の生育だけではありません。病気や害虫のリスクも増します。たとえば、温暖化によって本来は南方にしかいなかった害虫が、北日本や標高の高い地域にも広がっています。「ウンカ」や「アザミウマ」などの虫は稲に被害を与え、収穫前に一気に田んぼを枯らしてしまうこともあります。また、病原菌も温暖な気候で活動が活発になり、「疫病」や「うどんこ病」などの感染が広がりやすくなります。農家にとっては、防除(ぼうじょ=農薬の散布など)のコストと手間が増すばかりです。
他にも、暖冬や早春の高温により、開花や収穫のタイミングがずれ、本来の旬から外れてしまう収穫時期のずれが発生したり、生育不良・枯死、水不足や過度の暑さで作物が枯れてしまったりするケースも珍しくありません。気候の安定性が失われることは、農業にとって深刻な脅威なのです。
技術と工夫で立ち向かう現場
こうした厳しい状況の中でも、日本の農家たちは知恵と技術で気候変動に立ち向かっています。ビニールハウスに遮光ネットをかけて日差しを調整したり、地温を下げるマルチシートを使用したりと、遮光・被覆資材を導入することで作物のストレスを軽減しています。また、種まきや収穫時期を前倒しにすることで収穫時期の調整をし、猛暑のピークを避ける工夫もなされています。
さらに最近では、大学や研究機関で「高温に強い品種」の開発が進んでいます。たとえば、お米では2018年に農研機構が開発した「にじのきらめき」や「恋の予感」など、耐暑性に優れた新品種が注目されています。野菜や果樹でも、耐病性・耐暑性を備えた品種への転換や新種開発が進んでいるのです。また、ICT(情報通信技術)を活用した「スマート農業」も普及中です。ドローンやAI、IoT(モノのインターネット)を活用し、温度や湿度、土壌の水分量などをセンサーで自動測定し、AIが最適な灌水や施肥のタイミングを判断するシステムが拡大。現場の負担を減らしつつ、高品質な農産物の安定供給に貢献し、気象変動への柔軟な対応を可能にしています。
このように農業の現場では、最新の技術を活用しながら日本の農作物を猛暑に対応できるよう進化させつつ、「経験」と「判断力」を持つ農家の現場対応が日本の農業を支え、日々我々消費者に農作物を供給してくれているのです。
消費者の私たちにできること
気候変動による環境の変化は、いずれ「食の安定供給」にも影響を与えるかもしれません。すでに、スーパーでは「野菜の値段が高い」「果物の味が落ちた」といった変化に気づいている人も多いはずです。私たち消費者にできることの一つは、「旬のものを選ぶ」「形が悪くても地元産を買う」といった、農業の実情に寄り添った購買行動です。また、地元の農家を応援する産直市場や、フードロス削減に貢献するサービスの活用も小さな一歩となります。そして、何より大切なのは、「食べ物が簡単に手に入るのは当たり前ではない」という意識を持つこと。その意識が、これからの食と農業を守る力になるのです。
まとめ
農業は、自然との対話の中で成り立つ営みです。人間の技術が進歩しても、気候に抗うことは簡単ではありません。しかし、猛暑が「いつも通り」を壊す今だからこそ、農家の知恵と科学の融合が必要とされています。地球が熱を持ち始めた今、作物を育てるという行為そのものが、挑戦となっています。しかし、それでもなお自然と向き合い、畑に立ち続ける人々がいます。暑さに耐えながら、実った作物は、私たちの食卓に並びます。その一皿に、気候の現実と、農家の粘り強い工夫が詰まっていることに、少しでも思いを馳せてみてください。それが、これからの“おいしい”を守る一歩になるかもしれません。