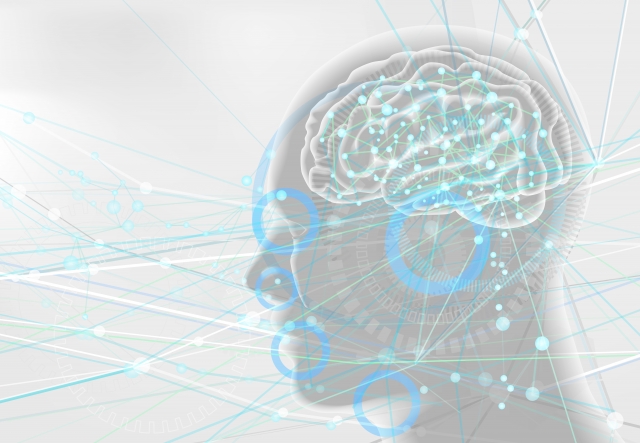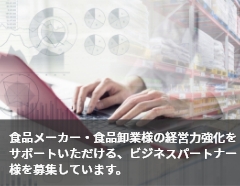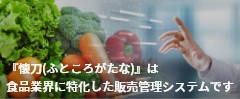陸上養殖がひらく、食と環境の新時代

はじめに
いま、世界中で「陸上養殖」が注目を集めています。これは、海や川ではなく、陸上の水槽で魚を育てる新しい養殖スタイルです。海の環境に左右されず、安定した生産を可能にすることから、気候変動や資源減少といった水産業が抱える課題を解決する手段として期待されています。また、食料安全保障や環境保全、地域産業の新しい形としても注目されており、今まさに「海から陸へ」というパラダイムシフトが進んでいるのです。
海の養殖が抱える課題
日本は世界有数の水産国として発展してきましたが、近年、その土台が揺らいでいます。漁業資源の減少、漁業者の高齢化、海水温の上昇、赤潮や台風など自然災害の激甚化。これらの要因によって、海面養殖の現場では魚の大量死や出荷量の不安定化が問題となっています。
さらに、沿岸部での過密養殖による環境負荷も無視できません。排泄物や残餌による海底の汚染、病原菌の拡大など、従来の養殖方式には限界が見え始めています。
「環境を守りながら、持続的に魚を育てる方法はないのか」、その問いに応える形で登場したのが、陸上で魚を育てるという新しい発想です。
陸上養殖とは何か
陸上養殖は、陸上に設置した水槽やプールで魚を育てる方式です。海水や淡水をポンプでくみ上げ、人工的に水質・温度・酸素量などを管理します。最大の特徴は、閉鎖循環式システムを活用する点です。この方式では、養殖水をろ過・殺菌しながら再利用するため、海や川に排水をほとんど流さずにすみます。そのため、自然環境への影響を最小限に抑えながら、安定した生産を続けることができるのです。
また、海の環境に左右されないため、赤潮や低酸素水塊の影響を受けることもありません。台風や波浪の被害を心配する必要もなく、内陸部でも魚を育てることができます。つまり、陸上養殖は「海の制約を超える技術」なのです。
テクノロジーが変える水産業
陸上養殖の発展を支えているのが、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)といった先端技術です。センサーを用いて水温・pH・溶存酸素などを常時モニタリングし、AIが自動的に最適な環境を保つよう制御します。魚の映像を解析して成長度合いや健康状態を把握するシステムも開発されており、職人の経験や勘に頼っていた養殖が、データに基づく“精密な生産”へと変わりつつあります。
また、給餌(えさやり)も自動化され、魚の食欲や成長スピードに合わせて最適な量を与えることが可能になりました。これにより、餌の無駄を減らしつつ、品質を均一に保つことができます。こうしたテクノロジーの導入によって、陸上養殖は効率化とコスト削減を同時に進められるようになっているのです。
新しい産業のかたち
陸上養殖の大きな魅力は、「海から離れても水産業ができる」ことです。これにより、これまで漁業とは縁のなかった地域や企業にも新たなチャンスが生まれています。内陸の工業地帯や都市近郊に施設を設けることで、消費地に近い場所で新鮮な魚を生産・供給することが可能です。輸送コストの削減や鮮度保持の面でも優位性があり、地域の雇用創出や地産地消の拡大にもつながっています。
また、陸上養殖には異業種からの参入が相次いでいます。IT企業がデータ分析のノウハウを活かして参入したり、食品メーカーがブランド魚の開発を行ったり、さらには電力会社、建設・不動産・テレビ局まで最先端の養殖施設を建設するなど、水産業の枠を越えた連携が進んでいます。ベンチャー企業によるクラウド型養殖管理システムの開発も進み、養殖の“見える化”が加速しているのです。
持続可能な社会を支える技術へ
陸上養殖は、環境面でも多くのメリットを持っています。海水を繰り返し使うことで水資源の消費を抑え、排水をほとんど出さないため、海洋汚染の心配がありません。
また、施設内の水質を一定に保つことができるため、抗生物質や薬剤の使用を減らすことができ、“クリーンな魚”を育てることができます。
さらに、気候変動の影響を受けにくいため、長期的な視点での安定生産が可能です。人口増加による食料需要の拡大が予想される中で、陸上養殖は「未来の食料インフラ」としての役割を担うことが期待されています。特に海外では、ノルウェーやシンガポールなどが国家戦略として陸上養殖を推進しており、日本もその潮流の中で存在感を高めつつあります。
残された課題と展望
一方で、陸上養殖はまだ発展途上の産業でもあります。課題のひとつが、初期投資とランニングコストの高さです。水槽設備やポンプ、浄化装置、モニタリング機器などの導入費用は高額であり、また、水温管理などに必要な電力コストも無視できません。採算性を確保するためには、効率的な運用やブランド価値の高い魚種の選定が重要です。
もうひとつの課題は、「魚本来の味」をどう引き出すかという点です。自然の海流やプランクトンなど、海の中でしか得られない風味や運動量が魚の味に影響します。
そのため、陸上養殖では水流の強さや光の当て方、餌の成分などを工夫し、自然に近い環境を再現する研究が進められています。
今後は、再生可能エネルギーとの組み合わせによる電力コスト削減や、AIを用いた最適運用の高度化などが進むことで、より持続可能なビジネスモデルが確立されていくと考えられます。
山口県が挑む「新たなウニ養殖」
日本海と瀬戸内海、二つの海を抱く山口県は、古くから豊かな漁場として知られています。なかでもウニは、アワビやサザエと並び、県を代表する重要な水産資源のひとつです。令和3年の漁獲量は125トンで、全国9位に位置しています。
しかし近年、藻場の減少によりウニの餌となる海藻が不足し、身入りの悪い「痩せウニ」が増加。市場価値が低いだけでなく、餌を求めて残った海藻を食い尽くしてしまうため、藻場の再生を阻む一因にもなっています。まさに、海の生態系全体に影響を与える深刻な課題です。こうした状況を打開しようと、山口県では令和5年度から未利用資源や特産品を活用した新たなウニ養殖に着手。県産の農産物や水産副産物を餌として再利用し、身入りや風味を改善。香りづけなどによる「山口ならではのウニ」作りを進めています。
この取り組みは、環境保全と地域資源の循環を両立する、山口発の新たな海の再生モデルです。
まとめ
陸上養殖は、単なる技術革新ではありません。それは、人と海の関係を再構築する新しい産業モデルでもあります。自然を消費するのではなく、自然と共存しながら生産を行う。この発想は、環境問題が深刻化する現代において、非常に大きな意味を持っています。
また、地域に新たな雇用と学びの場を生み出し、若者が関われる“次世代型の漁業”としても期待されています。テクノロジーと人の知恵が融合し、海の恵みを持続可能な形で未来へつなぐ。その先に広がるのは、食の安定だけでなく、環境・経済・社会がバランスよく循環する新しい社会の姿です。私たちはいま、海の上ではなく、陸の上から「海の未来」を創りはじめています。陸上養殖は、まさに“持続可能な水産業”への第一歩であり、食と環境の新時代を切り拓く希望の技術と言えるでしょう。