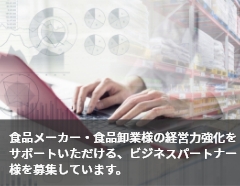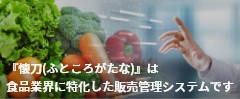IT投資はコストか?──中小食品メーカーのDX成功事例に学ぶ

はじめに
食品業界に身を置く中小企業の経営者にとって、「IT投資はコストか、それとも将来のための資産か」という問いは避けて通れません。特に近年は、HACCP(ハサップ)対応の義務化により、食品製造の現場ではデジタル化の必要性が一層高まっています。しかし、中小企業にとってHACCP対応は「コスト負担」や「人手不足による運用困難」といった課題が山積みです。紙帳票での記録作業は時間も手間もかかり、確認・保管・検索に多くの労力を割かざるを得ません。さらに、人の手による記録はどうしても記入漏れや誤記入が発生しやすく、監査時の不安材料になっていました。
そこで注目されているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)によるHACCP対応の効率化です。今回は、実際にDXを導入し成功を収めた中小企業の事例を取り上げ、そのポイントを探っていきます。
HACCPとは?
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point:危害要因分析重要管理点)は、食品の安全を守るために国際的に導入されている管理手法です。原材料の受け入れから製造・出荷に至るまでの各工程に潜むリスクを分析し、特に重要な管理ポイントを継続的に監視・記録することで、安全性を保証します。日本でも2021年から原則として全ての食品関連事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務づけられ、中小企業にとっても避けられない取り組みとなりました。
HACCPを導入することにより危害要因を重点的に管理することで食中毒のリスクを低減でき、衛生管理が徹底されることで製品の品質が向上します。さらに、HACCP認証を取得することで消費者の信頼を得ることができるというメリットがあります。しかし、温度や湿度のチェックを紙に記録し続ける作業は手間がかかり、ミスも多発します。これが「HACCP対応はコストがかかるだけ」というイメージを強めてきました。
食品業界が直面する「2025年の崖」
経済産業省が2018年に提唱した「2025年の崖」とは、老朽化した既存システムや複雑化した業務プロセスが、DX推進の大きな障壁になることを指す言葉で、2025年までに課題を解決できなければ、日本経済に最大12兆円の損失が生じると警告されています。
食品業界も例外ではなく、多数の業界の中でも特に深刻といえる状態です。人材不足・需要減少・食品ロス・複雑な規制対応という複合的な課題を抱えており、これらを乗り越えるためには、DXによる業務効率化やトレーサビリティ強化が不可欠です。HACCP対応をはじめとするデジタル化の取り組みは、単なる義務対応にとどまらず、未来の競争力を左右する重要な投資といえるでしょう。
中小食品メーカーのDX成功事例
HACCPの義務化は特に中小企業にとって大きなプレッシャーとなっています。ところが、その「義務」をきっかけにDXを導入し、競争力を高めた企業も存在します。課題を抱えながらも成功をつかんだ事例をみていきましょう。
①美味フーヅ株式会社(徳島県):タブレット活用で「自主的な記録文化」を定着
徳島県で地域資源を生かした生ドレッシングを販売する美味フーヅ株式会社では、製造過程での安全性に自信はあるものの、HACCP対応において紙ベースの記録作業、記録管理の手間と正確さに不安を感じていました。そこで同社は、食品業界向けの記録デジタル化システム「ツクルデ」を導入。タブレット端末を用い、現場で直接データ入力を行う仕組みを整えました。これにより、記録はリアルタイムでクラウドに保存され、異常があればその場でアラートが表示されるため、迅速な対応が可能になりました。さらに効果的だったのは、若手従業員が積極的にタブレット記録を行うようになった点です。「現場での記録が面倒」という不満が減り、自主的にHACCP対応が行える文化が根づきました。その結果、国際的なHACCP認証(SGS)を取得し、大手取引先との商談でも信頼性が向上。単なる業務改善にとどまらず、新しい取引機会の拡大へとつながったのです。
②株式会社三和食鶏:クラウド活用で記録・トレーサビリティを一気に効率化
鶏肉の加工を手がける三和食鶏では、HACCP対応を進めるにあたり「膨大な記録作業」と「トレーサビリティ管理」に課題がありました。紙帳票を保管しても検索に時間がかかり、必要な情報をすぐに取り出すことが難しかったのです。ここで同社が導入したのは、クラウド型のHACCP記録管理システム「ezHACCP」。従業員はタブレットやPCから直接記録を入力でき、データはクラウド上に自動保存されます。入力ミスや記録漏れがあればリアルタイムでアラートが出るため、監査時の不安要素も大幅に軽減されました。特に効果を発揮したのはトレーサビリティです。出荷後に問題が発生した場合、関連記録を瞬時に検索でき、過去のデータから異常の有無を即確認可能になりました。これにより、取引先への対応スピードが向上し、「信頼されるパートナー企業」としての地位を確立しています。
他にも、飲食店やレストランでのHACCP対応の負担は少なくありません。特に加熱調理の温度記録は「食品が中心部まで適切に加熱された証拠」として重要ですが、手作業で温度を測り記録する方法では、どうしても漏れや不正確さが生まれてしまいます。
ある飲食チェーンでは「ペーパーレス記録計」を導入し、加熱時の温度や時間を自動で記録・保存できるようにしました。作業者は計測器を操作するだけで、データは自動でクラウドに保存され、後からいつでも確認可能です。これにより「記録作業そのものの負担」を削減しつつ、監査対応でも高い信頼性を示せるようになりました。
これらの事例は、「人手不足の現場でも導入しやすいシンプルなDX」として、今後さらに広がっていく可能性があります。
IT投資は「コスト」ではなく「未来への投資」
こうした事例を通じて見えてくるのは、DXは「大規模投資が必要なもの」ではなく、中小企業でも現場にフィットするシステムを部分的に導入することで大きな成果を上げられるということです。中小企業にとって、新しいシステム導入は「コスト」として重く感じられることも多いでしょう。しかし、今回紹介した事例のように、DXを通じて得られるのは単なる効率化ではありません。
従業員の働きやすさ改善により、記録の手間削減やモチベーションが向上します。また、トレーサビリティ強化をすることで監査対応の信頼性が向上し、新しい取引機会の拡大ができ、認証取得や大手企業との取引を促進することができるのです。
これらは企業の持続的な成長につながる大きな価値です。つまり、HACCP対応のDXは「義務を果たすためのコスト」ではなく、経営基盤を強化するための戦略的投資と捉えることができます。
まとめ
HACCP義務化は中小企業にとって大きなハードルである一方で、DX導入によって業務効率化や信頼性向上を実現するチャンスでもあります。美味フーヅや三和食鶏のように、規模の小さな企業でも現場に合ったDXをうまく取り入れることで、新しい価値を生み出す成功事例が次々と生まれています。
「DXは大企業だけのもの」と思われがちですが、実際には小規模な改善の積み重ねが大きな成果につながります。これからの食品業界において、HACCP対応とDXは切り離せない関係にあり、取り組みの有無が競争力の差となって表れるでしょう。今こそ、中小企業が未来に向けて一歩を踏み出す好機です。